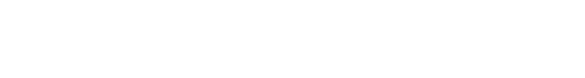フリーランス支援情報ポータルは、フリーランス法の紹介、説明、相談窓口の紹介、セミナー情報を提供しています。
フリーランス法の解説explanation
- TOP
- フリーランス法の解説
- 発注者の禁止行為(その2)
※取引適正化の範囲に限ります。
発注者の禁止行為(その2)
※取引適正化の範囲に限ります。
2025.3.3
3 発注事業者の禁止行為
(1)7つの禁止行為
前記2の要件を満たす発注事業者には、以下の7つの禁止行為が定められています(フリーランス法5条)。禁止行為に該当する行為は、たとえフリーランスとの間での合意に基づき行う場合でも、フリーランス法違反となることに注意が必要です。
●受領拒否
●報酬の減額
●返品
●買いたたき
●購入・利用強制
●不当な経済上の利益の提供要請
●不当な給付内容の変更・やり直し
以下、それぞれ解説します
(2)受領拒否
受領拒否とは、フリーランスの責めに帰すべき理由がないのに、フリーランスが納入してきた物品や情報成果物の受領を拒むことをいいます。「受領を拒む」には、発注の取消や納期の延期により発注時に定められた納期に受け取らないことも含みます。なお、役務の提供委託は受領拒否の対象になりません。
「フリーランスの責めに帰すべき理由」があるとして受領を拒否できるのは、①フリーランスの給付の内容が委託内容に適合しない場合や、②フリーランスの責任により納期遅れがあり、不要になった場合です。
例えば、発注事業者が、発注日から1週間後であった納期を、発注日から2日後に一方的に変更して、フリーランスが短縮された納期に間に合わなかったことを理由に商品の受領を拒否するような場合、受領拒否になります。
(3)報酬の減額
報酬の減額とは、フリーランスの責めに帰すべき理由がないのに、発注時に定めた報酬を減額することをいいます。発注時に定めた額から1円でも差し引けば減額になります。「フリーランスの責めに帰すべき理由」として減額できる場合は、受領拒否と同様です。
例えば、発注事業者(ゲーム開発会社)が、顧客(ゲームメーカー)の業績悪化により制作予算を削減されたことを理由に、フリーランスの報酬をあらかじめ定めた金額より引き下げて支払う場合、減額になります。このような事情であれば、フリーランスも報酬の減額に同意していることもあり得ますが、前記のとおりフリーランスが同意していても違法です。
また、フリーランスとの合意がないにもかかわらず、報酬をフリーランスの金融機関口座に振り込む際に、振込手数料を差し引いて支払うのも減額に当たります。振込手数料をフリーランス負担とすることは、その旨を発注前に書面又は電磁的方法で合意し、振込手数料実費の範囲内で差し引く場合には適法です。
(4)返品
返品とは、フリーランスの責めに帰すべき理由がないのに、フリーランスから納入された物品や情報成果物を受領後に返品することをいいます。「フリーランスの責めに帰すべき理由」として返品できる場合は、受領拒否と同様です。
契約不適合があった場合でも、常に返品できるわけではありません。検査で直ちに発見できる不適合の場合は、発見後速やかに返品する必要があります。直ちに発見できない不適合の場合、原則として受領後6か月以内(一般消費者に対して6か月を超える保証期間を定めている場合には、当該保証期間内で最長1年まで)に返品が可能です。ただし、発注事業者が受入検査をしていない場合や、フリーランスに受入検査を委託しているものの書面や電磁的方法で委託していない場合には、不適合があっても返品できません。
例えば、発注事業者が、商品を購入した顧客から不具合のクレームがあったことを理由に、受領後6か月を経過した商品をフリーランスに返品した場合は、違法になります。
(その3)に続く